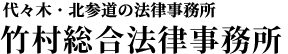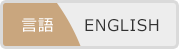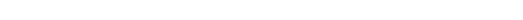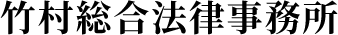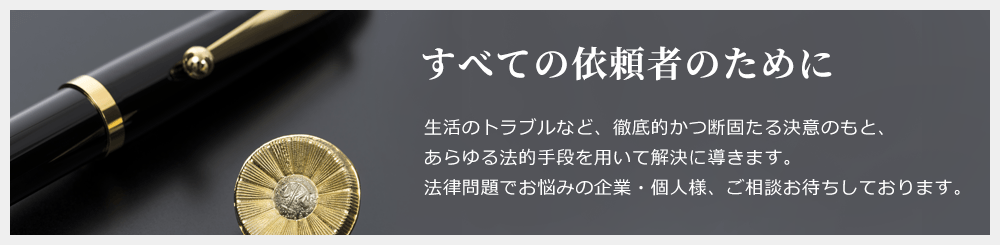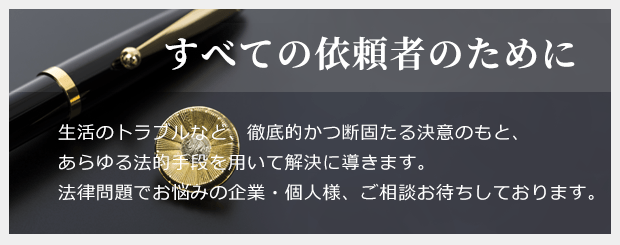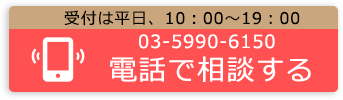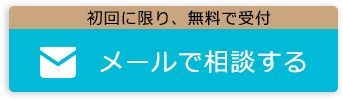取扱業務
離婚問題について
離婚問題に直面しているご依頼者様のお気持ち・ストレスは痛いほどよくわかります。事情によりますが、できれば話し合い・協議段階からご相談・ご依頼いただいたほうが合理的な解決が早くなるように思います。 当事務所代表の竹村公利弁護士は、米国ペンシルバニア大学で離婚分析学を受講するなど、離婚問題に向き合って弁護士20年になります。
離婚の方法
離婚には大きく分けて、以下の4種類の方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
以下、私の経験・弁護士の役割も踏まえて、ご説明いたします。
協議離婚
その名のとおり、ご夫婦間での協議により、離婚する場合です。
財産分与、親権、養育費、慰謝料等の諸条件を協議により合意・決定し、離婚届を役所に提出して離婚します。
特に親権や財産でもめることがなければ、もっとも簡便で早い離婚の方法です。
- 各国離婚法を比較しても、裁判所を経ないという意味では、日本に特有の離婚方法と言えます。
- 弁護士の役割⇒後日の紛争を防ぐため、通常、「協議離婚書」の作成をお勧めしています。経済的給付が長期にわたる場合などは、公正証書にすることもあります。
調停離婚
「夫婦関係調整の調停」手続きにおいて、調停委員を交えて話し合った結果、お互い離婚に合意し、離婚調書を作成して離婚する場合です。
- 調停期日は原則1カ月に1回程度の目安で予定されていきます。離婚そのもの、あるいは離婚する条件でもめれば、1年ほどは時間がかかります。
- 弁護士の役割⇒調停申立において申立書を作成し、また、離婚期日においても代理人として依頼者様の利益を守るべく代弁します。
審判離婚
実務上は、調停手続きにおいて、離婚自体については合意しているものの、ある条件について合意に至らない場合に、当該条件について裁判所の判断にゆだねて離婚するものです。
- 実務上、ほとんど使われていません。
- 弁護士の役割⇒審判において、依頼者様の利益が最大になるべく、主張・資料の提出を行うことになります。
裁判離婚
その名のとおり、裁判所の判決によって離婚するものです。法律上、離婚裁判の前に調停手続きを経ることが義務付けられています。
- 裁判離婚は多くはありませんが、実際には裁判離婚にもつれ込むケースは少なくありません。ただ、実際に判決で離婚するケースは確かに少なく、実務上は、裁判官の和解勧告により、和解によって離婚、あるいは離婚届の提出が行われています。
- 弁護士の役割⇒裁判離婚においては、訴状の作成から期日への出席、準備書面の作成、証拠の収集、提出まで、依頼者と協同し、大きな役割を担います。
離婚の成立する原因
相手方に離婚をする意思がない場合、離婚原因の存在が認められなければ離婚することができません。離婚原因は、法律で定められており下記の5つの離婚原因に分類されます。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
浮気のことです。ただし、浮気と言っても原則として、精神的なものでは足りず、性的関係まで必要です。不貞行為は、一度きり継続的なものかを問いません。金銭に基づく女性との性的関係も不貞行為にあたります。
悪意の遺棄
正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないことをいいます。もっとも、少しでも協力・扶助をしなければこの要件が認められるわけではなく、婚姻関係が破綻していると認められる程度の遺棄が必要です。別居については同居義務に違反することになります。生活費の不払い等も程度により悪意の遺棄となりえます。実際には悪意の遺棄で一番多い原因がこちらになると思われます。
3年以上の生死不明
生死不明の理由は問われません。この要件にあたる場合、裁判を提起することになりますが、人事訴訟においては、必ず証拠調べを行う必要がありますので、その後に判決となります。
回復の見込のない強度の精神病
強度の精神病とは、統合失調症、早発性痴呆症、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などの高度の精神病であり、夫婦としての交流が出来ないほどに強度なものである必要があります。健康状態と高度の精神病の中間にあるアルコール中毒、モルヒネ中毒、ヒステリー、神経衰弱症等は、ここでいう強度の精神病には該当しないといわれており、かえって悪意の遺棄と主張される場合もありますので、注意が必要です。
その他婚姻を継続しがたい重大な理由
その他婚姻を継続しがたい重大な理由
上記4つ以外の婚姻関係が破綻し回復の見込みのないことをいいます。具体的には、暴行・虐待、重大な病気、宗教活動、勤労意欲の喪失、犯罪行為、親族との不和、性格の不一致などがあります。
親権
離婚の際の子供の問題としては、
- 親権者を誰にするのか、
- 養育費をどうするのか、
- 親権者以外の親と子との面接の機会をどうするのか、
などがあります。まずは親権についてです。離婚に際しては、子の親権者を定めなければなりません。親権は、婚姻中は子の父母が共同で行いますが(民法818条)、離婚する場合には、父母のどちらか一方を単独の親権者と定めなければなりません(民法819条)。親権の内容は、身上監護と財産管理に大別されます。身上看護とは、子を肉体的に監督・保護し、精神的成長のために教育することをいい、財産管理とは、子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となることをいいます。親権者を決める基準は、誰が親権者になることが子の利益、子の福祉に適合しているかという観点から、父母や子供を取り巻く様々な事情を考慮して決定されることになります。実務上は、母性優先の原則、現状尊重の原則、子の意思の尊重などが重視されており、多くの場合に母親が親権を取得しています。
コメント 日本においては、母性優先の原則、つまり、幼い子は原則として母親に親権が行く慣行があります。しかし、最近では、この原則も絶対的なものではなくなりつつあります。養育費
養育費とは、子を育てていくために必要な食費、被服費、住居費、教育費、医療費、保険料、娯楽費、その他の費用をいいます。
親は子が一人前になるまで子を扶養する義務がありますので、養育費の負担義務は、自己が負担可能な限度で負う生活扶助義務ではなく、負担者の余力の有無に関わらず資力に応じて相当な責任を負う生活保持義務であると考えられています。
養育費をいつまで支払うかについては、一般的には未成熟子が成年に達したときとすることが多いですが、父母の学歴などの家庭環境、資力などにより個別に定めることができます。
例えば、父母の学歴や生活レベルなどから子に大学教育などの高等教育を受けさせることが親の生活水準と同等の生活水準を維持させるために必要といえる場合には、子が大学を卒業するまでとすることが多いようです。
養育費の金額がどのように決められるかですが、実務上は、夫婦の収入及び子の人数・年齢に応じた養育費算定表があり、これに当てはめて算出されています。
面接交渉
面接交渉とは、離婚後、子を引き取らなかった親が、子と面接したり話をしたりすることです。 親は、子の福祉・利益を害しない限り、子と面接交渉する権利があると考えられています。 実務上は、子の年齢や負担などを考慮して、面接交渉の回数や方法を定めています。 面接交渉の実情としては、調停成立事案の約半数以上において、月1回以上の面接交渉が定められています。 子を別れた相手と面接させることに不安がある場合には、第三者に立ち会ってもらう方法があります。 例えば、「社団法人家庭問題情報センター」(通称FPIC)という団体においては、元家庭裁判所調査官が第三者の立場で面接に付き添ったり、カウンセリングなどのサービスを有料で提供したりしています。
コメント 離婚に関して全てを専門家に任せたいという場合には、弁護士へ相談することをお勧めしています。財産分与について
財産分与とは、離婚に際して夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。婚姻期間中に蓄積した財産は半分ずつ分与する、というのが離婚の際の原則です。ただし、どちらかの寄与度がはっきりと大きいといえるような場合は、平等ではなく寄与度に応じて分与割合を定めている例もあります。どんな財産が分与の対象になるか?結婚してから二人の力で築き上げた財産は全て対象になります。婚姻時に既に所有していた財産等の特有財産は分与の対象になりません。
- 財産分与の対象となる財産
- 住宅などの不動産
- 預貯金
- 株式等
- 会員権
- 絵画や骨董品などの経済的価値のある物
- 家庭用電化製品や家財道具類(※実際には新品でなければあまり価値はありません)
- 退職金
- 年金
- 家族経営の財産
- 財産分与の対象とならない財産
- 自分の親から相続した財産
- 婚姻時に既に所有していた財産
- 婚姻の際に実家から持ってきた財産
その他にも多くの財産を考えられますが、あくまでも財産を特定させなければなりません。相手がどのような財産を持っているのか確認をしておく必要性があります。
コメント 日本においては、原則、2分の1とされていますが、実際には慰謝料を考慮したり、離婚後の生活保障を考慮したりするなど、多様な解決方法が図られています。年金について
年金分割の手続き
- 年金情報の提供を受ける夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。
- 按分割合について話し合い夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。
- 公正証書等の作成夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。年金分割の記載事項は下記の通りです。当事者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨当事者間で合意した按分割合
- 年金分割請求管轄の社会保険事務所に年金分割の請求をします。請求期限は離婚の翌日から2年以内となっていますので、注意が必要です。
男女・内縁問題について
最近は内縁、いわゆる「事実婚」の夫婦が増えています。 「内縁」とは、単に婚姻届を出していないだけで、結婚する意思をもって実質的に夫婦と同じように結婚生活を営んでいる関係のことです。 愛人関係や単なる同棲と混同されやすいのですが、内縁の夫婦には婚姻届を出した夫婦と同じように同居義務・協力義務・扶助義務があり、貞操を守る義務もあります。 正式に婚姻していなくても、両者が婚姻の意思を有しながら相当期間共同生活を継続している場合に、その関係を解消するといったときには離婚の場合と同様に慰謝料や財産分与の問題が生じることがあります。 これを内縁の解消といいます。したがって、長い間共同生活を続けながら、その関係が破綻したような場合には、まずは自分が有する権利を確認するために、弁護士に相談した方がよいといえるでしょう。 内縁解消についても、当事務所にご相談ください。
内縁関係の男女の間にうまれた子供について、内縁関係は“法律上の婚姻に準ずるもの”と考えられているので、慰謝料・財産分与は認められます。 これに対して、内縁関係の男女の間にうまれた子供と父親は、届出がないままでは何ら関係を持ちませんので、養育費を請求することはできません。しかし、父親が子供を認知すれば親子関係が成立し、父親の子供に対する扶養義務も発生しますので、養育費の支払いも可能になります。
コメント 熟年離婚に限らずですが、女房の方は考えた末で、夫の方は寝耳に水という事案は多いと言えます。離婚を考えている方、疑問なことがあれば当事務所の法律相談をご利用ください。熟年離婚
増え続ける熟年離婚、熟年離婚は夫の退職を機に今でも多い現状です。 何年か前に「熟年離婚」というテレビドラマでも話題になりました。 熟年離婚は夫が定年退職した後に多いと言われています
妻:夫が家庭にいなかったからなんとか耐えてこられたのに、これから2人きりなんて冗談じゃないとある意味恐慌状態になっている。夫が毎日家にいるという事態を迎えてバランスを失って火を噴く。夫:定年退職したら女房と2人でのんびり過ごしたいと思っているが実は夫婦関係が内部から腐っていることに気づかないまま何十年もきている。
しかし、このような事態を招いたのは双方の責任とはいえ、人生は短いのです、多くの時間をむなしい婚姻生活と虚構の日々で費やしてしまったことの代償はあまりに大きいのではないでしょうか。子供がいる場合には次世代にも悪影響が出ます。こういった夫婦の子供達は、将来きっと同じような夫婦生活を送るんでしょうね。そして、こんな風に言うと思います。「愛情?そんなもの夫婦に必要ないよ、うちのパパもママもそんなもの一つも持ち合わせていなかったけど、ふつうに何十年も夫婦やってたよ。」本当の熟年離婚の悲劇はここにあるのです。
コメント 熟年離婚に限らずですが、女房の方は考えた末で、夫の方は寝耳に水という事案は多いと言えます。離婚を考えている方、疑問なことがあれば当事務所の法律相談をご利用ください。離婚事件の弁護士費用
| 着手金 |
|
|---|---|
| 報酬金 |
|
弁護士をお探しの方へ、ご相談方法について
弁護士をお探しの方について電話・メールでの初回法律相談を無料にて提供させて頂いております。初めて弁護士へご相談をされる方は来所して面談という形でお話させることをおすすめします。